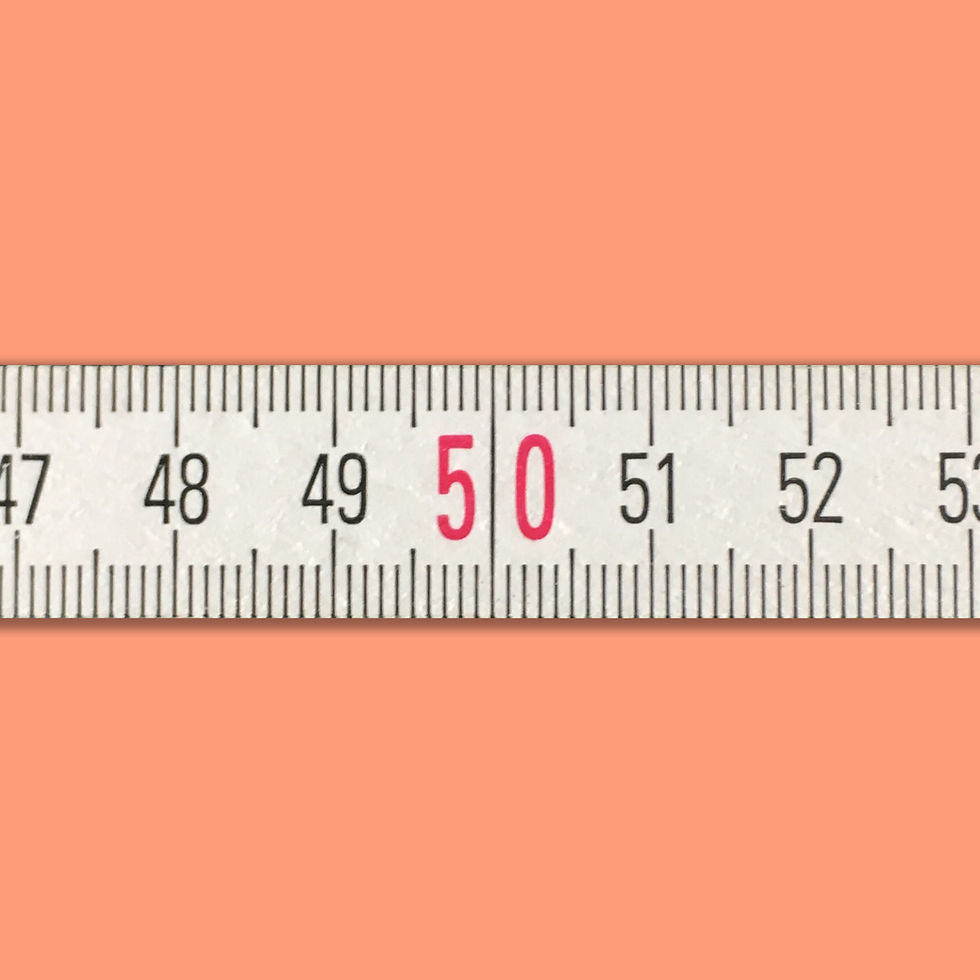AI画像認識・高速画像処理による収穫物の良品・不良品判別のススメ
- 2025年9月24日
- 読了時間: 12分
更新日:2025年10月9日

日本の農業では、収穫物を市場や量販店に出荷する前に必ず「外観検査」が行われます。
現場では 従来型の機械選別(重量・サイズ・色分け) が一次検査を担い、その後に 人手による目視確認 で傷や病害、微妙な色ムラなどを補っています。
この「機械+人手」の二重チェックは精度は高いものの、以下の課題を抱えています。
出荷量がピークを迎える時期に、人手を十分に確保できない
作業員ごとに判定基準が異なり、ばらつきが生じる
長時間作業で疲労し、誤判定が増える
人件費負担が大きく、経営を圧迫
こうした課題を解決する技術として「AI画像認識・高速画像処理による自動外観検査」が注目されています。
現状の従来型選別+人手検査の仕組み
国内における農作物の品質検査は、長年にわたり 「従来型選別機による一次検査」+「人の目による最終確認」 という二段構えで運用されてきました。
この流れは果実・野菜・穀物など多くの品目で共通しており、農協の選果場や出荷組合、個別の農業法人において広く採用されています。
重量・サイズによる選別
仕組み/方法
コンベア上で秤を用いて重量を測定、またはローラー間隔で直径を測定
計測結果に応じてエアやフラップで仕分け
対象作物
リンゴ・みかん:大玉・中玉・小玉に区分
ジャガイモ・サツマイモ:サイズ別袋詰め用
キュウリ:長さ・曲がり具合を自動判定
色彩選別機による選別
仕組み/方法
カメラや光学センサーで表面色を数値化。熟度や色ムラを基準として仕分け
RGBに加え近赤外波長を用いることで精度を高めるケースも増加
対象作物
リンゴ:赤色度で熟度を判定
みかん:色の濃淡で等級区分
トマト:熟度別仕分け(未熟・完熟・過熟)
大豆・小豆:着色不良や異常粒を排除
比重選別機による選別
仕組み/方法
水槽に沈める「水選」
送風で軽いものを飛ばす「風選」等 比重差を利用
対象作物
米:虫食いや未熟粒を浮遊・沈降で除去
小麦・大豆:充実度の低い粒を分離
柑橘類:比重で内部のスカスカ果(浮き果)を除外
透過光・X線検査機による選別
仕組み/方法
光やX線を透過させ、内部空洞や障害の有無を検出
透過率や画像解析結果に基づき仕分け
対象作物
リンゴ・梨:内部の空洞や蜜入りを確認
柑橘類:中身がスカスカの果実を除去
米・穀物:内部割れや異物混入の検出
従来型選別機だけでは、出荷品質を完全に保証することはできません。そこで欠かせないのが、人の目による最終確認です。
目視による検査・選別
検査対象
表面の細かな傷やスレ、軽微な変色
病害斑点(黒斑、カビ、ウイルスによる異常)
機械では拾いきれない微妙な「見た目の印象」
熟練者の判断力
消費者が購入時に感じる「見た目の美しさ」「鮮度感」を総合的に評価できるのは人手ならでは
特に高級果実やギフト用途では、人の選別がブランド価値を支える要素となっています
ここまで述べたような、「従来型選別+人手検査」は下記のようなメリットがあり、現在広く採用されています。
経験と勘の活用
農産物は自然物であり、機械的な基準だけでは測れない要素が多い。熟練検査員は「経験則」で判断できる
臨機応変な対応
病害が流行した年や天候不良の影響で外観傾向が変わっても、人間は即座に柔軟に対応できる
消費者への安心感
「人の目で見ている」という事実は、品質保証の上で大きな信頼につながる
人手による検査の課題・限界
従来型の選別機と人手検査を組み合わせた方式は、長年にわたり日本の農作物流通を支えてきました。大量処理に強い機械と、人間ならではの直感的な判断を補完的に組み合わせることで、安定した品質を維持してきたことは確かです。
しかし、農業を取り巻く環境が変化し、国内流通市場に求められる品質保証レベルが高まる中で、この方式だけでは対応が難しくなってきています。以下では、現場で顕在化している主な課題を6つに整理し、それぞれを詳しく解説します。
労働力不足の深刻化
農業就業人口は年々減少し、高齢化も進んでいます。農林水産省の統計によれば、2024年時点で基幹的農業従事者の平均年齢は69.2歳に達しており、若年層の新規参入は限定的です。

従来の検査方式では、収穫ピーク時に臨時雇用を大量に確保しなければならず、地域によっては労働力を確保できずに選別が追いつかないケースが増加しています。人材が集まらないことで「収穫したのに出荷できない」という事態にも繋がる可能性があります。
作業者ごとの判定基準のばらつき
人間の目視検査は柔軟である一方、基準が属人的になりがちです。同じリンゴでも、ある検査員は「A品」と判断し、別の検査員は「B品」とすることが珍しくありません。
特に新人作業員や短期アルバイトでは判定基準のブレが大きく、結果として出荷品の品質の均一性が損なわれます。
また、ブランド産地や高級果実の出荷では、消費者が求める「見た目の美しさ」の水準が高く、判断に迷うケースが多発します。このばらつきはクレームや返品の要因となり、農協や出荷組合にとっては信用問題に発展するリスクを抱えています。
作業効率と精度の低下
収穫期には一日に数万個単位の農産物が選別ラインを流れます。機械がふるい落とせない微妙な傷や病害は最終的に人が拾うため、検査員は数時間にわたり集中して外観をチェックし続けることになります。
長時間作業による疲労は集中力の低下を招き、誤判定率が上昇します。このように、人間に依存する方式では物理的限界が避けられません。
コスト構造の硬直化
従来の方式は人件費依存が大きく、規模拡大すればするほどコスト負担も比例して増大します。特に選果場では、検査工程が人件費全体の30〜40%を占めるケースもあり、経営を圧迫する要因となっています。
また、検査員を確保するために地域外から短期雇用を呼び寄せると、労務コストだけでなく宿泊費・交通費なども発生します。結果的に「売上が伸びても利益が出にくい構造」になり、設備投資や次世代技術への投資余力を削いでしまう状況に陥ります。
トレーサビリティ・記録の不十分さ
近年、国内市場においても「出荷履歴」や「検査記録」を残すことが求められています。特に食品リコールやクレーム発生時には「いつ、どのような基準で検査したのか」を遡れる仕組みが必要です。
しかし従来型の「人の目による判定」では、判定プロセスをデータとして残すことが困難です。作業日誌や手書き記録は残されても、個々の農産物の画像や判定根拠までは保存されません。そのため、問題が発生した際に原因追及や再発防止が難しいという課題があります。
品種・出荷形態の多様化への対応不足
国内市場では、季節限定品やブランド果実、差別化商品の開発が進んでおり、出荷形態がますます多様化しています。例えば、同じトマトでも「完熟トマト」「フルーツトマト」「加熱用トマト」と用途別に基準が変わり、従来型機械と人手検査だけでは柔軟に対応するのが難しくなっています。
AI画像認識・高速画像処理による判別技術
従来型選別機と人手検査の組み合わせでは、どうしても「取りこぼし」が発生し、人材不足やコスト増につながってきました。こうした背景から、良品・不良品を瞬時に判別できる新技術 の導入が進みつつあります。
特に注目されるのは、高速画像処理・AI画像認識といった領域です。以下では、それぞれの技術を掘り下げ、どのように現場課題を補完できるのかを整理します。
高速画像処理による外観検査
従来型の色彩選別機は「平均的な色」には強いものの、果皮表面に点在する小さな斑点や病害の痕跡を捉えるのは苦手としており、色彩選別機だけでこれらの不良を除去しようとすると、正常品も一緒に除去してしまうなどの問題が発生します。
高速画像処理は、従来の色彩選別機では対応できなかった「微細な欠陥」の判別を可能にします。
アプローチ例:
高速カメラで収穫物を複数方向から撮影
FPGA(Field Programmable Gate Array)を利用し、数千~数万画素単位で並列処理を実行
1個あたり数ミリ秒(ms)で画像解析が完了
適用事例:
トマトの裂果(割れ)や色ムラをリアルタイム判別
リンゴの細かな打撲痕や黒斑病を検出
米や豆類の「微細な割れ」や「虫食い痕」を自動抽出
事例:高速画像処理によるイネいもち病の判定

AIUB (バングラデシュ)のTanvir Ahmed達による研究では、稲の葉に発生する「いもち病」を効率的かつ高精度に検出するためのしきい値処理型画像解析手法(OTSU法)を提案しています。
本研究はRGB画像をHSV空間に変換後、メディアンフィルタによるノイズ除去と、青色チャネル上でのOTSUしきい値処理によって損傷領域を二値化し、形状特徴(面積・軸長・ソリディティなど)を抽出して病斑を特定することで、CNNなどのように大量の学習データを要することなく、高速かつ高精度で病変を検出することに成功しています。
平均検出精度は95.34 %を達成し、従来法より約2.5〜2.7 秒高速であった。提案法は、他の植物病害(褐斑病・シースロットなど)にも応用可能で、シンプルな画像処理ベースのエッジAI的アプローチとして、農業分野における自動病害診断の有効性を示した。
ディープラーニング (AI画像認識) による高精度判定
AIの中でも特にCNN(畳み込みニューラルネットワーク)は、外観の複雑なパターンを学習し、人間に近い判断を自動化できます。
アプローチ例:
過去の良品・不良品データを大量に学習
色・形状・質感など複数の特徴を同時に判別
適用事例:リンゴの表面欠陥を判別するマルチカメラ選別システム

韓国全南大のJu-Hwan Lee達の研究では、リンゴ表面の欠陥(擦り傷・変形・腐食斑など)を高精度に検出するマルチカメラベース欠陥選別システムを提案しています。
従来の単一のカメラでの検査では死角が生じ、異常を適切に検知できない問題がありましたが、本事例では、3台の固定カメラと同期制御された搬送ローラーを組み合わせ、果実を一定角速度で回転させながら全周撮像を実現しています。
本撮影方法で得られたマルチビュー画像を畳み込みニューラルネットワーク(CNN)で解析し、欠陥の有無をリアルタイムに判定するとともに、蒸留によるモデル軽量化を行うことで、組込みハードウェア上での推論最適化を達成。
300個のリンゴを対象とした実験では、分類精度93.83%、1果実あたり平均処理時間2.84秒、CNN単体推論時間0.069秒を記録しました。
AI画像認識・高速画像処理導入に向けたポイント
新しい技術としてAI画像認識や高速画像処理を導入すれば、従来方式に比べて検査効率や品質の標準化は大きく進展します。しかし一方で、「導入すればすぐに全ての課題が解決する」というわけではなく、現場の実情に合わせた準備や調整が不可欠です。ここでは、農作物検査システムを現実に導入する際に直面しやすい留意点を整理します。
データ不足と学習用サンプルの準備
AIによる判別は学習データに大きく依存します。しかし、農作物の不良品は発生率が低いため、十分な数を揃えることが困難です。
典型的な課題
黒斑病やカビなど特定の病害は発生時期が限られ、サンプル収集が難しい
「正常」データは数万枚以上収集可能でも、「不良」データは数百枚にも満たない
解決策
GAN(Generative Adversarial Network)等によるデータ拡張でサンプル数を補う
Few-Shot Learning(少数ショット学習)や不良データそのものを生成するAIとの組み合わせにより、「不良データが少ない」状況でも学習可能な体制を整える
撮影環境と照明条件の最適化
農産物の外観は、照明の角度や強さに大きく影響されます。従来の色彩選別機では、照明条件の変動によって精度が低下し、人手が補ってきました。AIを導入しても、この課題は依然として存在します。
典型的な課題
晴天・曇天・夕方など時間帯によって色味が変化する
選果場ごとに照明の設置環境が異なり、モデルをそのまま適用できない
解決策
拡散光やリング照明、多方向照明などを組み合わせて均一な光を確保する
AIモデルに「異なる照明条件で撮影した画像」を学習させ、ロバスト性を高める
入力画像に対してリアルタイムで輝度補正・色補正を行う前処理技術を導入する
現場オペレーションとの適合性
農業現場に新しい技術を導入する際に最も重要なのは、「既存の作業フローを大きく変えないこと」です。高度なシステムでも、現場作業員が使いにくければ定着せず、結局人手依存に戻ってしまいます。
典型的な課題
機械が検知した不良を人が再確認する場合、検査工程が複雑化する
新しいUIや操作方法に慣れるまでに時間がかかる
解決策
従来のラインに「後付け」できる構成を採用し、導入初期は人手検査と併用する
操作画面はシンプルに設計し、「良品/不良品」の結果を直感的に表示する
検査員がAI判定を理解できるよう、アラート画像を記録して後から確認できる仕組みを整える
コストとROI(投資対効果)の見極め
導入を検討する上で必ず問われるのが、「どのくらい費用をかけ、どのくらい回収できるのか」です。高価なシステムを導入しても、処理量や作業効率が改善しなければROIが合わず、経営的に持続できません。
典型的な課題
AI用GPUサーバや高解像度カメラの初期投資が大きい
ライン停止を伴う大規模な設備更新は、短期的に出荷量減少を招く
解決策
FPGAベースの高速処理装置など、低コストで低消費電力な方式を採用する
クラウド利用とオンプレ処理を組み合わせ、ランニングコストを最適化する
PoC(概念実証)で小規模導入し、投資回収可能性を見極めた上で本格展開する
アルジェントテクノロジーの高速画像処理
株式会社アルジェントテクノロジーは、高速画像処理・画像認識・三次元計測 に強みを持つ技術ベンチャーです。
高速画像処理・ディープラーニング技術・撮影条件設計技術を組み合わせ、農産物のリアルタイム検査に対応
検査フロー設計からAIモデル構築、データ拡張まで一気通貫で支援
豆類・果実・野菜など農産物の多様な検査ニーズへの対応
「収穫物のAI判別を実現したい」とお考えの農業法人・食品メーカー様は、ぜひ弊社にご相談ください。