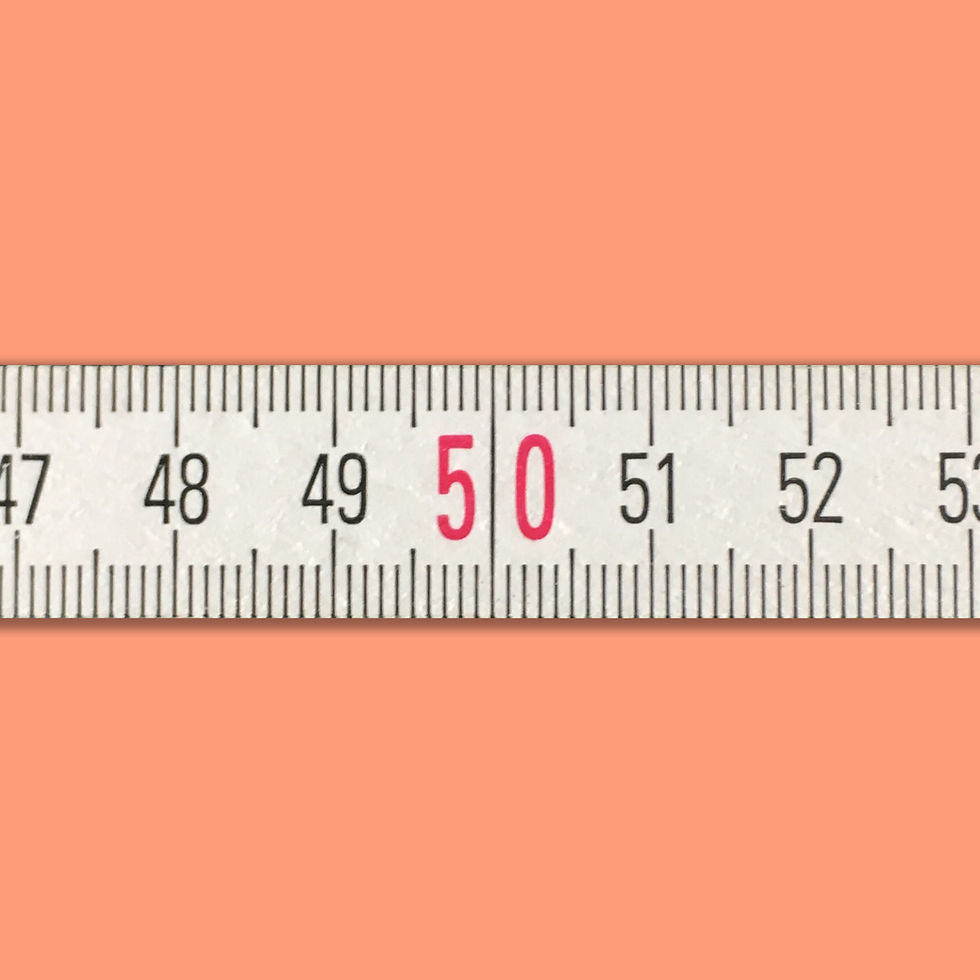病害虫を早く発見!AIとドローンで広がるスマート農業
- 俊徳 大山
- 9月25日
- 読了時間: 11分
更新日:5 日前

病害虫の発生は農作物の収量と品質に直結する最大のリスク要因の一つです。国内では依然として多くの農家が 目視調査や経験則 に基づいて圃場を巡回し、病害虫を確認しています。
一方、このような従来型の手法では
広大な圃場を人手でカバーするのは困難
発見が遅れると被害が一気に拡大
薬剤散布コストや労力が増大
といった課題が深刻化しています。
こうした背景から、ドローン+AIによる病害虫の早期検知 が注目されています。従来の調査に比べ、広範囲を短時間でカバーし、AIによる画像解析で微細な変化を検出できるため、省力化・収量安定・品質保証 に大きく貢献します。
従来の病害虫検知方法と課題
農作物の病害虫を早期に検知し、被害を最小限に抑えることは、国内農業において収量と品質を安定させるために極めて重要です。これまで多くの農家や農協が採用してきた方法は、主に 「人の目による巡回調査」 と 「トラップ・フェロモン調査」 です。
これらは長年の経験に支えられ、一定の効果を発揮してきました。しかし、近年の圃場規模の拡大や就業人口の減少により、その限界が顕在化しています。以下では従来手法の詳細と、それぞれが抱える課題を整理します。
人手による巡回と目視調査
最も基本的で広く行われている方法が 農家や作業員が圃場を歩き、作物を直接観察する目視調査 です。葉の表面や裏、茎、果実を順番に確認し、病斑・食害痕・変色などを探し出すものです。
具体的な流れ
朝や夕方など気温が安定している時間帯に圃場を巡回
作物の葉や茎、果実をランダムにチェック
斑点や変色、虫の姿を確認した場合、発生場所と程度を記録
必要に応じて部分的に農薬散布を実施
課題
労働負荷の高さ:水田や果樹園など広大な圃場を隅々まで歩いて調べるのは膨大な時間と体力を要する
見落としのリスク:初期の病斑やごく小さな害虫は、経験豊富な農家でも見落とすことがある
属人的な判断:判定は作業者の経験に依存し、同じ病害でも「軽度」と判断する人もいれば「深刻」とみなす人もいる
季節的制約:梅雨や夏の猛暑時には巡回が難しく、調査頻度が低下する
トラップ・フェロモンを用いた調査
病害虫の発生傾向を把握する方法として、トラップやフェロモン剤を用いた調査 も広く利用されています。これは対象害虫の習性を利用して誘引し、捕獲数や発生時期を記録するものです。
代表的な手法
フェロモントラップ:性フェロモンを発する誘引剤で特定の害虫を捕獲(例:コナガ、果樹害虫)
ライトトラップ:夜間に光へ集まる虫を捕獲し、個体数を数える
粘着シート:葉や支柱に設置し、アブラムシやコナジラミなど小型害虫を捕獲
課題
対象が限定的:誘引効果のある害虫には有効だが、全ての病害虫をカバーできない
サンプリング精度の問題:一部のトラップで捕獲数が少なくても、圃場全体に大量発生している可能性がある
共通する課題と限界
従来のいずれの方法にも共通して次の課題が存在します。
人的依存の高さ→ 調査精度は人材の経験と労力に左右され、再現性に乏しい
広域カバーの困難さ→ 数ヘクタール規模の圃場全体を網羅するのは非現実的
初期兆候の検出困難→ 病害虫が広がる前に見つけるのが理想だが、従来手法では見逃しやすい
データ活用の制約→ 記録はノートや表に手書きされることが多く、分析や共有が難しい
これらの課題は、国内農業の生産性と持続可能性に直結しています。例えば、稲作における「いもち病」、果樹園における「カメムシ被害」、施設栽培における「うどんこ病」など、いずれも初期段階での発見遅れが大きな被害拡大を招くことが知られています。
従来の調査方法では初期兆候を確実に捉えるのが難しく、結果的に農薬散布の回数や量が増え、コストと環境負荷が増大するという悪循環に陥りがちです。
ドローンによる圃場モニタリング
従来の人手や衛星・航空機による調査では限界があった「病害虫の初期検知」ですが、ここ数年で急速に普及したのが 農業用ドローン です。国内では農薬散布用としてすでに数万台規模で導入されていますが、ドローンの真価は 空からの圃場モニタリング にもあります。
高性能カメラやマルチスペクトルセンサーを搭載したドローンは、従来不可能だった精度で圃場の状態を「見える化」し、病害虫や生育異常の兆候を捉えることができます。
広域観察と作業効率の劇的向上
農家が徒歩で1ヘクタールを調査する場合、数時間かかるのが一般的です。これに対し、ドローンであれば10〜15分程度で同面積を空撮可能です。さらに、圃場全体を上空から「鳥瞰的」に把握できるため、偏ったサンプリングに頼る必要がなくなります。
事例
稲作農家が出穂期の水田をドローンで空撮し、葉色のムラを可視化。窒素不足のエリアや病害が広がりつつある区画を早期に特定でき、施肥や防除の効率が大幅に改善した事例が報告されています。
高解像度カメラによる詳細観察
高解像度カメラを用いることで、葉の黄化や斑点など病害虫の兆候を数cm単位で把握できます。特に果樹園や施設栽培での活用が進んでおり、従来は人が梯子に登って確認していたような葉裏の異常も、上空から確認可能になりました。
事例
リンゴ園:上空からの空撮で葉の変色を把握し、斑点落葉病の初期兆候を確認
トマト栽培ハウス:ドローンによる定点撮影で葉かび病の進行度を可視化し、被害拡大前に防除
マルチスペクトル・熱赤外線カメラの活用
ドローンの真価は、可視光カメラに加えて マルチスペクトルカメラや熱赤外線センサー を搭載できる点にあります。これにより、肉眼では判別できない作物の「ストレス状態」を検知できます。
マルチスペクトル解析
植生指数(NDVIなど)を算出し、葉のクロロフィル量を推定。これにより光合成能力や栄養状態を可視化し、病害虫被害の前兆を把握できます。
熱赤外線解析
葉の温度上昇は蒸散作用の低下を示します。害虫の吸汁や病気で気孔が閉じると葉温が上昇するため、病害虫発生の早期サインを捉えられます。
事例
稲作:マルチスペクトル解析により「いもち病」発生エリアを早期特定。必要箇所に限定した薬剤散布が可能に
柑橘園:カメムシ被害で樹勢が弱った区画を熱赤外線カメラで検知
定点観測と時系列データの蓄積
ドローンは 定点飛行プログラム を組むことで、同じ経路・同じ高度から定期的に圃場を撮影できます。これにより時系列データを蓄積し、病害虫や生育異常の「進行度」を数値化して把握できます。
1週間前には異常がなかったが、今日のデータでは葉色が変化 → 進行速度を把握でき、防除タイミングを最適化
時系列データをAIに学習させることで、次の発生予測にも活用可能
事例
茶畑における病害進行をドローンで観測。発生範囲を逐次確認することで、薬剤散布を30%削減できた事例が報告されています。
AIによる病害虫検知の仕組み
ドローンが圃場の広域データを収集するだけでは、病害虫の初期兆候を正確に特定することは難しい場合があります。
そこで重要になるのが、収集した画像データを解析し、「正常な作物」と「異常のある作物」を識別する AI技術 です。特にディープラーニングを中心とした機械学習手法は、農作物の病害虫検知に大きなブレークスルーをもたらしています。
画像解析と特徴抽出の基本的仕組み
従来は、病害虫検知のために「葉の緑色度」「斑点面積」などの特徴量を人間が設計(ハンドクラフト特徴量)していました。しかし、病害虫ごとに特徴が異なり、環境によっても変動するため、安定した精度を出すのは難しいものでした。
AI(特にCNN: Convolutional Neural Network) を利用することで、この課題は大きく改善されました。CNNは画像から自動的に特徴を抽出し、葉の色や形状の微妙な変化を人間以上の精度で検知できます。
例
トマトの葉かび病 → 葉に現れる淡黄色の小さな斑点を自動検出
稲のいもち病 → 葉に広がる紡錘形の病斑を識別
リンゴの斑点落葉病 → 色の変化と葉の形態異常を同時に抽出
正常/異常判定のロジック
AIによる判定の仕組みは大きく2つに分けられます。
教師あり学習(Supervised Learning)
正常・異常のラベル付きデータを大量に学習
CNNが「これはトマト葉かび病」「これは健全葉」と判定できるようになる
データ量が多い場合に高精度
異常検知(Anomaly Detection)
正常な作物データを学習し、「正常パターンから外れたもの」を異常として検出
未知の病害虫や新たな病原菌にも対応可能
データ不足の現場に適している
データ不足を補う技術
農業分野でAIを導入する際に最も大きな課題の一つが「病害虫データ不足」です。健全な作物画像は大量に集められる一方、病害虫の発生は時期や環境に依存するため、不良データを十分に確保できません。
これを解決するために以下の技術が活用されています。
データ拡張(Data Augmentation)
既存の病害画像を回転・反転・色調補正などで加工し、データを水増し
GAN(Generative Adversarial Network)
本物に近い病害画像をAIが生成し、学習データを増やす
稲のいもち病やトマト葉かび病などで研究事例あり
Few-Shot Learning(少数ショット学習)
数枚の画像でも学習可能なアルゴリズムを利用
導入時の留意点
ドローン+AIによる病害虫検知は、従来の人手依存の調査に比べて大幅な効率化と精度向上をもたらします。しかし「導入さえすれば全ての課題が解決する」というわけではなく、実際の国内農業現場に適用する際にはいくつかの重要な留意点があります。本章では、導入にあたり特に意識すべき6つの観点を整理します。
データ不足と学習用サンプルの確保
課題
病害虫は季節や気候に依存して発生するため、十分な枚数の病害画像を集めるのは容易ではありません。例えば「稲のいもち病」は特定の環境下でしか顕著に発生せず、安定的にデータを収集できません。
解決策
GAN(Generative Adversarial Network)を用いた病害画像の生成
Few-Shot Learning(少数ショット学習)を活用し、数十枚でも学習可能なモデルを利用
環境条件と撮影精度への影響
課題
ドローンによる空撮は、天候・時間帯・太陽光の角度に大きく左右されます。晴天時と曇天時では葉色の見え方が異なり、AI判定に誤差が生じる恐れがあります。
解決策
撮影時間を午前10時〜午後2時など「光条件が安定している時間帯」に限定
マルチスペクトルカメラで可視光以外の情報を補完
AIに照度補正・ホワイトバランス調整を組み込み、環境変化に強いモデルを設計
法規制と運用上の制約
課題
国内ではドローン飛行に関して航空法や電波法の規制が存在します。特に「目視外飛行」「夜間飛行」「補助者なし目視外飛行」などは許可申請が必要です。また、農協や大規模法人で導入する場合でも、オペレーターの資格取得が必須となるケースがあります。
解決策
農業分野に特化した「農業用ドローンライセンス」の取得
国土交通省の許可・承認制度を事前に確認し、運用ルールを明確化
共同利用を前提に、農協単位での運用体制を構築
コストとROI(投資対効果)の見極め
課題
ドローン本体、カメラ(RGB/マルチスペクトル/熱赤外線)、AI解析基盤(クラウド・サーバ)の導入には相応のコストがかかります。小規模農家では初期投資を回収できるかが大きな懸念となります。
解決策
PoC(概念実証)段階から導入し、小規模で費用対効果を検証
農協や地域単位での「共同利用モデル」により費用分散
FPGAなど低消費電力・低コストのAI処理基盤を導入してランニングコストを抑制
データ管理とトレーサビリティ
課題
ドローンによる空撮で生成されるデータは膨大で、1回の調査で数十GBに達することもあります。これを無秩序に保管するとストレージが圧迫され、管理不能に陥ります。また、出荷先が求める「いつ・どの圃場で・どのように検査したか」の記録が不十分だと、品質保証に活かせません。
解決策
AI判定に影響した「特徴的な画像」のみを保存し、全数保存は避ける
クラウドとオンプレストレージを組み合わせ、保管ポリシーを明確化
トレーサビリティを意識した「検査ログシステム」を構築し、取引先に提出可能な形でデータを保持
現場オペレーターの教育と受容性
課題
熟練農家や作業員にとって、ドローンやAIによる病害虫検知は「人の目を機械が置き換えるもの」と映り、心理的抵抗感が生じやすいです。教育が不十分な場合、システムは導入されても実際には使われないというケースが国内でも散見されます。
解決策
ドローン+AIは「人の代替」ではなく「人の補助」であることを強調する
初期は「AI判定+人の確認」という二重チェック体制で運用し、信頼性を体感してもらう
説明可能なAI(XAI)を導入し、「なぜ異常と判定したか」を可視化することで現場の納得感を高める
まとめ
従来の人手やトラップによる病害虫調査は限界を迎えつつあります。ドローン+AIを導入すれば、
広域を短時間でカバー
初期兆候を見逃さず検出
精密防除による農薬コスト削減
出荷品質の安定化
といった効果が期待できます。これは国内農業における 省力化と品質保証の両立 を実現する現実的な解決策です。
アルジェントテクノロジーの高速画像処理
株式会社アルジェントテクノロジーは、高速画像処理・画像認識・三次元計測 に強みを持つ技術ベンチャーです。
FPGA+AIによるリアルタイム画像処理
ドローン向けカメラ環境設計とAI解析基盤の提供
病害虫検知・作物モニタリングの国内適用実績
「ドローン+AIで病害虫を早期検知したい」とお考えの農業法人/農協様・農家様・食品メーカー様は、ぜひ弊社にご相談ください。